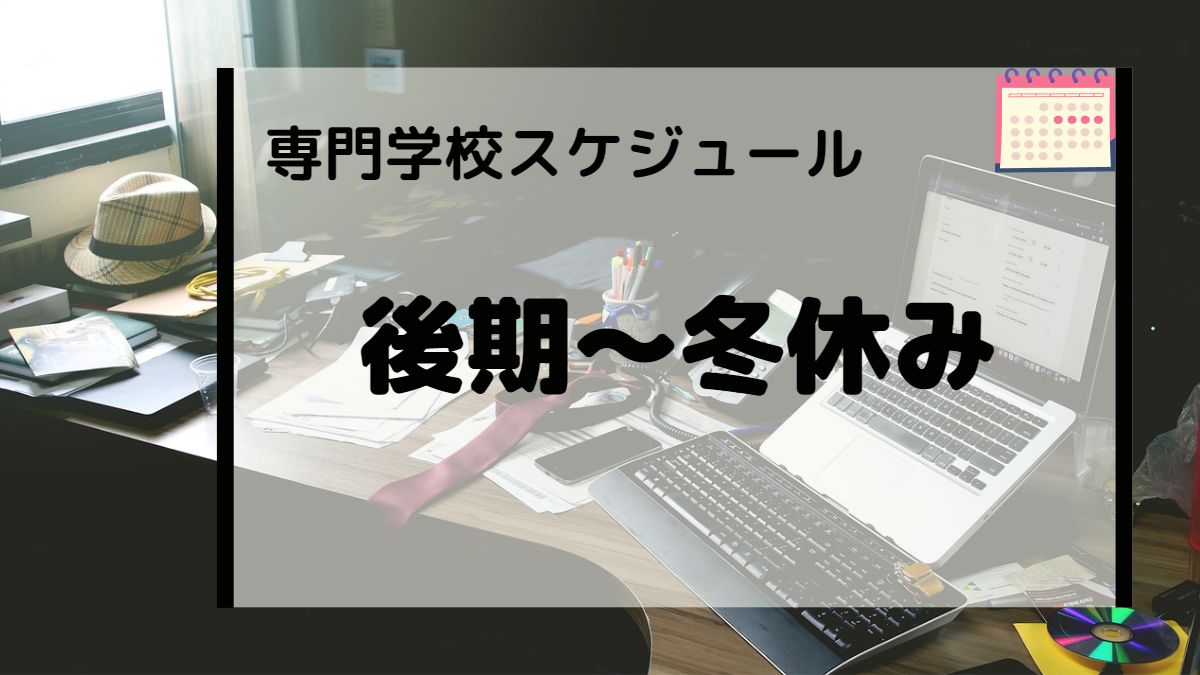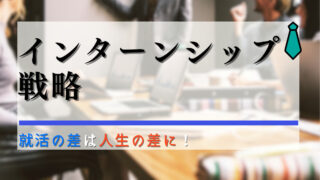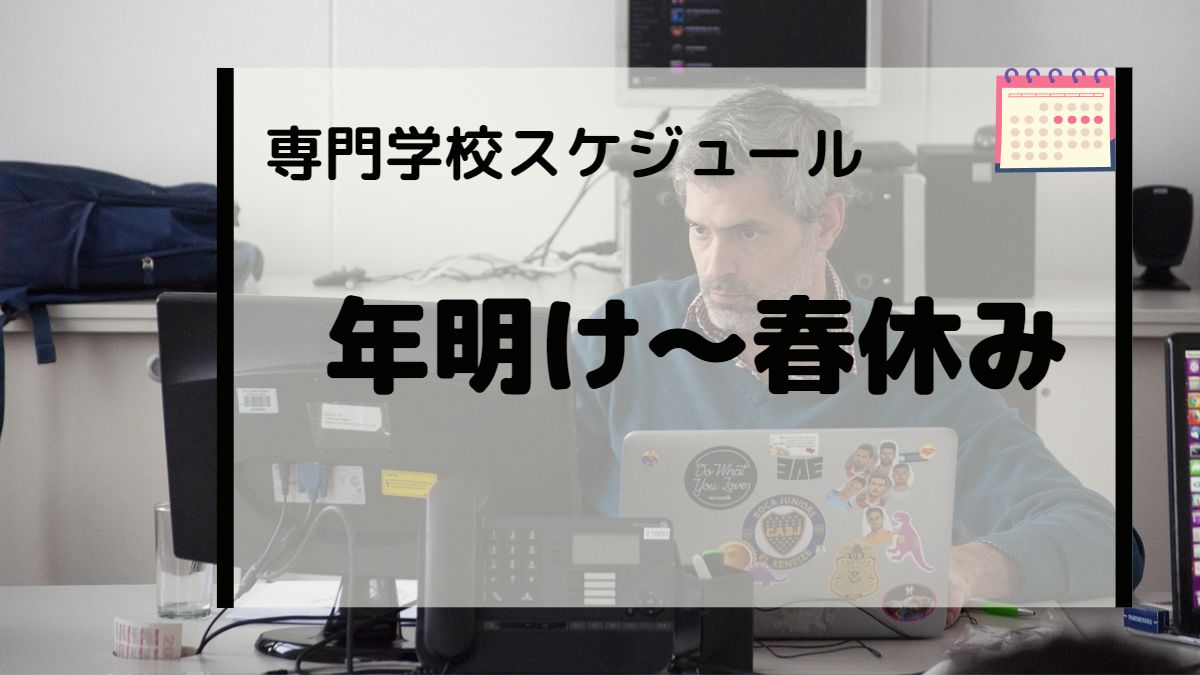2年課程は1年生後期・3年課程は2年生後期。人生を左右する重要な時期です。
前期までの授業・友達作りが成果を出すのが後期。
実習やグループ学習で友達関係から「仲間関係」になり、実践的な授業は「就職に直結」します。また、前期の授業内容の集大成として国家試験合格は人生の分岐点です。
あなたの卒業までの人生、就職してからの人生を大きく決めるのが、「後期」です。
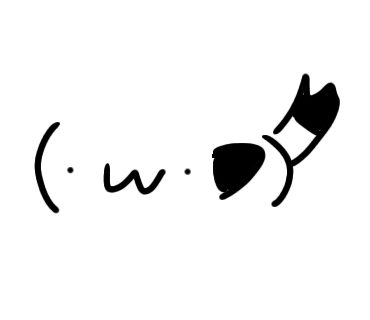
おおかた路線が決まるねー
私はIT専門学校で1年生を担当し、多くの学生さんの「人生の分岐」を見てきました。何回も担任をするうちに、「こんなことが起こるから、こういうことをしておこう」と「先読み指導」してきました。
この記事では、夏休み後から冬休みまでの「後期(前半)」について解説します。
| 学校生活 | 実施時期 | 最優先の成果 |
|---|---|---|
| 秋の国家試験対策期間(1日中) | 09~10月 | 国家試験の「合格」 |
| 後期授業(前半) | 11~12月 | 実習授業での「仲間」作り |
| 冬休み | 12~01月(2週間程度) | 「履歴書」の作成 |
| 後期授業(後半) | 01~02月 | 実習課題の完成 |
| 春休み+春の国家試験対策期間(1日中) | 03月(休み2週間、授業2週間) | 国家試験の合格 2年課程は就活 |
専門学校1年間の成果がでるかは、後期の実践にかかっています。
あなたが今後の学生生活を少しでも見通して、「ああやっておけば良かった」と後悔しない参考になれば、嬉しいです。
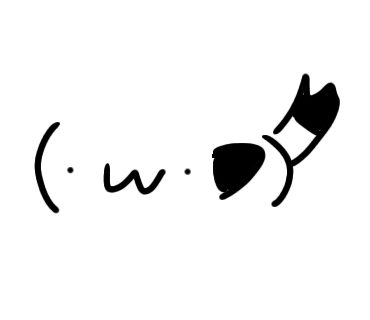
よろしくー
▼前もって読んでおきたい記事▼
▼次に読んで欲しい記事▼
いよいよ国家試験を受験 | 前期の集大成・学生人生の「分岐点」

IT専門学校の大目的は、国家試験「基本情報技術者」への合格です。
1年生前期の座学授業の全てを集約します。
基本情報技術者試験は4・10月実施から、コンピュータ受験(CBT)になっていつでも受験できるようになりました。
とはいえ、専門学校の授業スケジュールを考えると、あまり変化はありません。
- 1日缶詰の対策授業…03~04月(1年前期は除く)、09~10月
- 週1~2コマの対策授業…05~07月、11~02月
お薦めの受験期間は04~05月と10~11月です。1日缶詰の対策授業の直後ですから。
対策授業が終わると、どんどん忘れていって合格率が下がります。
自動車学校と同じです。自動車学校卒業から時間が経つほど、忘れてしまうことが多くなりますよね。
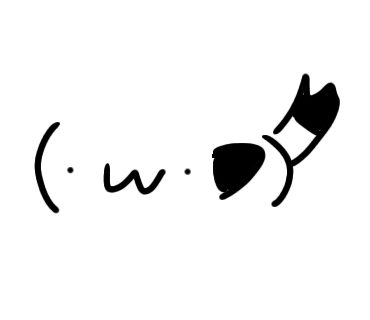
先延ばしにしないよー
対策授業では「過去問の演習と解説」を繰り返し行います。モチベーションの維持・受験へのストレスのバランスが重要です。
| 対策授業期間中 | 対策授業後 | |
|---|---|---|
| モチベーション | 高い | 低くなる |
| ストレス | 高くなっていく | 低くなる |
| 合格率 | 高まっていく | 低くなる |
ここで注意点。
授業つまらなくなったり、ストレスから体調不良になり始めるのもこの頃。
- 「毎日毎日」対策授業でつまらなくてうんざりする
- 「人生を左右する」国家試験に合格するかしないかストレス
受験勉強のストレスで、お腹が痛くなったり。試験問題が解けないから眠り癖や諦め癖がついてしまうのもこの時期です。
気持ちも分かりますが、息抜きをしつつ、とりあえず無駄な欠席をおさえましょう。
今一度、入学する前・直後の自分の目的や理想を思い返してみてください。
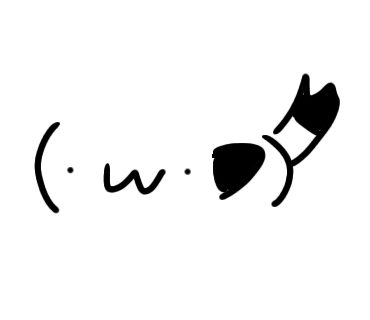
モチベは高くなくても
学校に行くぐらいにはしよー
後期の授業 | 実習とグループ活動で「就職に直結」

対策授業期間が終わると、いよいよ後期授業が本格的に始まります。
- 前期より詳細な座学…さらに高度な資格試験に向ける
- 実習やグループ授業…プログラミング実習、グループディスカッションなど
- 国家試験対策授業…週1~2コマの忘れ防止ていど
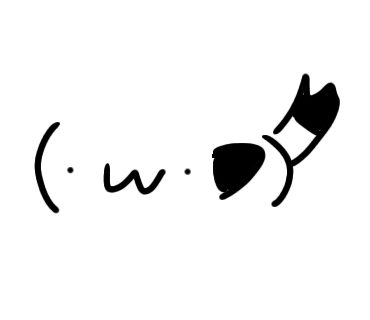
いよいよ実践的になるねー
特に重要になってくるのが、実習・グループ授業。
- 友達ができてるなら、教え合い楽しく
- 友達ができてなくても、礼儀・能力で仲間になるチャンス
学校はこれからグループ実習や卒業制作に入っていきます。就職したら部署で協力して仕事をします。
「友達」なのかは関係なく、「仕事仲間」と受け入れてもらうには、結局「グループで役割を果たす能力」。
プログラムができる、計算が得意などの学力的なことだけではありません。分かりやすく話ができるか、話しかけやすい人柄か、グループ全体の成功を考えているか、より良い方向へ向かう行動ができるかです。
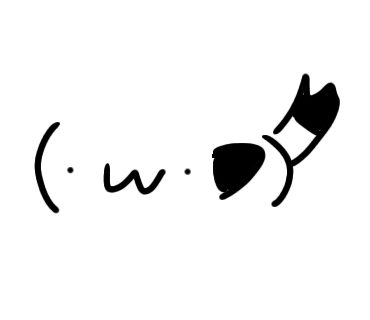
「使えるやつ」って
思われないとねー
1年生のプログラミング実習は「Progate」レベルでOK。
私のIT専門学校でも授業の最初の2~3コマはProgate(無料版)をしてもらっています。あなたも後期や夏休みに予習・復習として活用してくださいね。
お薦めは、Java言語・HTML&CSSで必須。あとは学校の授業内容に合わせて選んでくださいね。
あとはSQL・jQuery・PHP、優秀であればReact、Node.js(Web開発コース)をしておくと良いです。履歴書に「学校の勉強だけでなく、xxやxxの勉強をしました!」と書けますからね。
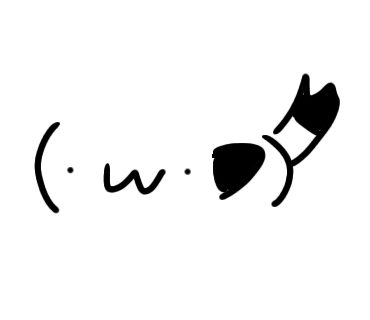
無料で学べるって
いい世の中だねー
冬休みまでに履歴書を | 準備が「遅れる」と準備が「増える」

履歴書は、前期と夏休みの行動を「集約」して書きます。
もし何もしてなかったら、今から始めましょう。
- 前期の学業…授業で「習った」はNG。どんな工夫・応用を書く
- 取得した資格…授業だけで対策はNG、合格してなくても勉強法を書く
- アルバイト…1日でも短期でも良いからやってみる
- インターンシップ…絶対に1社以上行く。受験したい企業なら絶対行く
- スポーツ…書きやすい。無遅刻無欠席でもつなげられる
- 趣味…読書・ゲーム・絵描き・音楽や映画鑑賞は避けたい
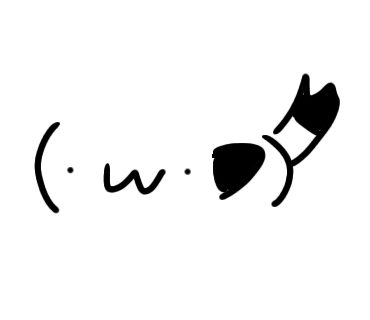
やってきたー?
今までの実績と履歴書に書ける相性は、以下の通り。
| 授業 | 資格 | アルバイト | インターンシップ | スポーツ | 趣味 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 得意な科目・資格 | ○ | ○ | × | △ | × | × |
| 学業以外の注力 | △ | △ | ◎ | ◎ | ○ | ○ |
| 特技や趣味 | × | △ | ○ | ○ | ◎ | ○ |
| 性格や特徴 | 以上を踏まえた上での結論 | |||||
| 志望動機 | △ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | △ |
履歴書はいろんなパターンがありますが、今回は一番細かい「4項目形式」でまとめました。
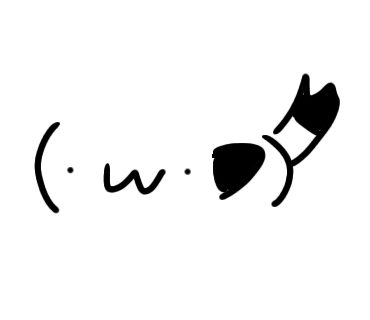
行動してないと
書くの大変だよー
アルバイトとインターンシップが最も書きやすいです。どちらも「就職」「労働」に直結しているので、企業さんがアピールと理解しやすいから。
- 「こんな風に働いていけるんだな!」
- 「働くことに前向きなんだな!」
一方で、各項目への被りは「多くても」2個まで。例えば「資格ネタ」を得意科目・学業以外の注力に書くと、アピールとして弱く思われます。
- 「またそのネタか、アピールネタないんだな…」
- 「うちで働いていけるんだろうか…」
アルバイトとインターンシップをしていないと、どんなことを書いても「言い訳」どまり。「学業専念」ではかなり苦しい履歴書作成・面接練習になってきますよ。
前期・夏休みの過ごし方は「専門学校の先生が薦める 1年生前期・夏休みを充実させる5つの行動」に詳しく書いています。今からでもアルバイト・インターンシップをすれば良いので、参考にしてくれると嬉しいです。
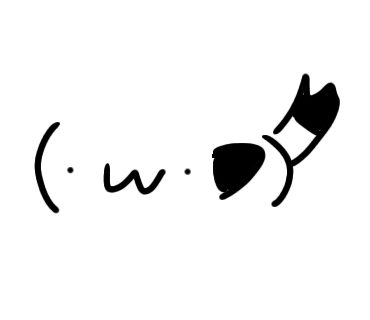
自己紹介じゃなくて
働けるアピールだからねー
冬休み | 就活準備の「ラストチャンス」!

2年課程は歳が明けると、もう就活が始まります。
1月からは企業説明会、3月には採用試験が始まります。大手企業は冬休みには募集を締め切っている場合もあります。
もう履歴書に時間をかけることはできません。企業を選び、書類準備・面接練習をしていかねばなりません。
冬休みが就職準備のラストチャンス。
- 履歴書が完成してないなら必ず完成させる(志望動機以外でOK)
- インターンシップやアルバイトをして実績を作る
- 趣味を突き詰めた合宿をしてみる
- 大手企業に応募したいならチェックする
- 業界分析や企業選別に入っておく(できれば)
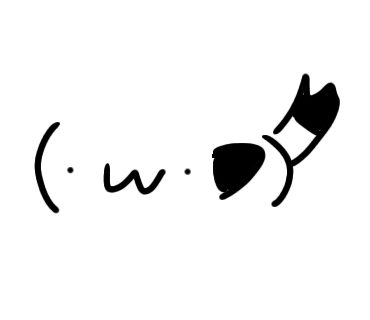
こっからは準備が
遅れると不利だよー
準備が遅れれば遅れるほど、やることが増えていきます。
志望動機や面接練習に時間をかけたいのに、まだ履歴書の「学業以外に注力したこと」を考えなきゃなんてことになります。
準備が遅れるほど、後の準備時間が圧迫され、応募が遅れます。「こんないい企業があったのに見逃したー」って後悔しても手遅れ。
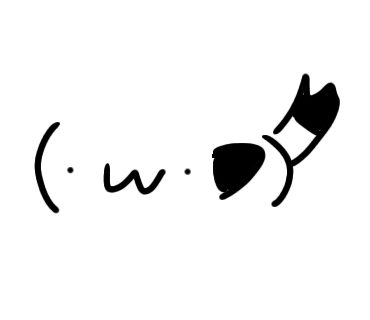
自分の人生が
どんどん絞れていくよー
まとめ | 後期前半は就職準備の「重要な時期」

ここまで読んで頂きありがとうございます!
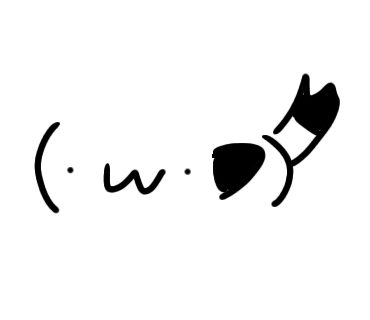
ありがとー
さくっとまとめましょう。
後期は「人生路線が決まる分岐点」です。
学校での路線も決まりますし、就職先のレベルもだいたい決まります。
- 国家試験…合格が人生を分ける。合格率とストレスのバランスが重要
- 後期授業…実習とグループ活動で、「仲間作り」と「仕事意識」で社会人へ
- 履歴書準備…今までの成果を。まだなら今からでも何かする
- 就活…「見逃した」では手遅れ。準備が遅れるほど、準備が増えて時間がなくなる
焦ってドタバタすることはないですが、「これから何があるのか」をしっかりと理解して、「少しだけでも」早めに準備をして、なるべく上手く泳いでいきましょう。
「これから何があるのか」を知っているのは先生です。だって、毎年毎年学生さんの人生を見てきてるわけですからね。
あなたの学校生活、どうやっていこうかを先生と話してみてくださいね。
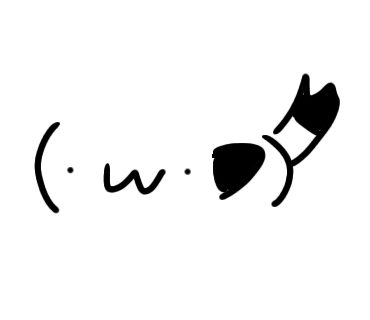
じゃ またー
▼次に読んで欲しい記事▼